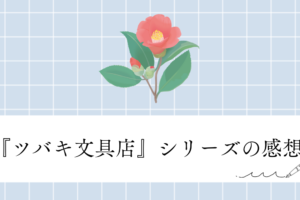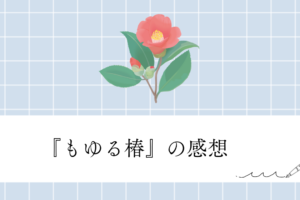私は、一人が好きだ。でも、「愉快な年下が無理やり家に住み着いてしまう…」なんて物語にどこかで憧れていたりする。もしかしたら、誰かにかまってほしいのかもしれない。『傑作はまだ』は、「孤独は嫌だけど一人が大好き(ホントはかまってほしい)」というちょっぴり強がりな人におすすめの小説。ネタバレしない程度に感想を書きたい。
『傑作はまだ』
瀬尾まいこ著
文春文庫
内容紹介
「永原智です。はじめまして」。そこそこ売れている50歳の引きこもり作家の元に、生まれてから一度も会ったことのない25歳の息子が、突然やってきた。孤独に慣れ切った世間知らずな加賀野と、人付き合いも要領もよい智。血の繋がりしか接点のない二人の同居生活が始まる……。明日への希望に満ちたハートフルストーリー。(裏表紙より)
著者紹介
瀬尾まいこ
1974年大阪府生まれ。大谷女子大学文学部国文学科卒業。2001年「卵の緒」で坊ちゃん文学賞大賞を受賞し、翌年、単行本『卵の緒』でデビュー。05年『幸福な食卓』で吉川英治文学新人賞を、09年『戸村飯店 青春100連発』で坪田譲治文学賞を、19年『そして、バトンは渡された』で本屋大賞を受賞。(そでより一部抜粋)
感想
主要2キャラの現実的な性格設定と、いい人しか出てこない空想的なストーリーが両立している良作。心が温かくなる物語だった。何度も読み返したくなる。
本の裏表紙に書かれていた「引きこもりの作家」「孤独に慣れ切った世間知らず」、そして帯に書かれていた「ちょっとズレた父」という言葉から、主人公で父である「加賀野」に親近感を覚え、私はこの本を手に取った。私もまた、訳あって一人で引きこもりながらライターの仕事をしており、浮世離れした生活をしている。引きこもりの訳を話すと長くなるから省略するが、メンタルの問題ではない。小説家としがないライターでは雲泥の差ではあるけれど、パソコンに向かってマイペースに文章を打ち込んでいる作業自体は似たようなものだろう。人との関わりが薄い一人暮らしのフリーランス。そんなライフスタイルに共通点を感じた。本を選ぶとき、ついつい自分と似たところがある主人公の物語を手にしてしまう。そんな読書好きはきっと私だけではないだろう。
読み進めると、加賀野の性格と私の性格が予想以上に似ていることに驚いた。やることなすこと、「私もそうなるんだよねー」と共感してしまう。そして、「人付き合いも要領もよい」と紹介されている息子「智」は、私が過去に助けられた当時の勤務先の後輩にそっくりだった。要領がよいというより、言葉に嫌味がないのだ。人の言動にズレたところを見つけると容赦なくツッコミを入れるけれど、そこにはバカにする含みがなく、ただ面白がっている。まるでネコのおかしな行動を見て可愛いと笑う飼い主のように。自分と違う性質の人間を嫌ったり蔑んだりするのではなく、その違いを楽しんだり助けたりする「愛」がある人物なのだ。人に警戒心が強い私でも、智のような性格の後輩は信頼できて、たくさん助けてもらった。
この親子は、上手くいく。物語がスタートして間もなく、そう直感できた。
加賀野という人物は、多くの人から見ると架空の人物像に見えるかもしれない。けれど、実は現実にそこそこ存在している。そして、加賀野のような人と付き合う術を知らない人間に「人生、悪くない」と思わせてくれるのは、たいてい智のような性格の人間なのだ。この緻密な性格設定に、思わず膝を打った。
ただし、現実は厳しい。浮世離れした人間は屈託のない人間に惹かれ、屈託のない人間はみんなに好かれる。だからよほど気に入ってもらえない限り、私生活において、みんなの人気者が浮世離れした引きこもりの世話を焼いてくれることはない。
しかし、この物語の中で、加賀野と智は親子であり、智から接触してきている。きっと上手くいくだろう。
物語が進むと、智との交流を通して、加賀野の生活は少しずつ変化していく。しかし、決して成長はしない。これが加賀野の成長物語であったなら、説教くさい駄作になってしまっただろう。50歳を超えて、人間の性質が変わることはないのだ。成長はしないけれど、今までに知らなかった感情を知る。そして、人生の楽しみがひとつ、ふたつ、増える。これは、成長の物語ではなく、救済の物語だ。閉じていた扉が、ゆるく開いていく。
ストーリーには直接関係がない要素として、加賀野が書いている小説が断片的に紹介される。これが実に面白くなさそうなのだ。そこそこ売れている作家という設定のはずだけれど…。読者としては、ツッコまざるを得ない。図らずも物語に参加してしまう。登場人物との距離がグッと近づき、私は、智の友だちポジションで読んでいたように思う。
最終章は、もはやおとぎ話である。「いや、そーはならんやろ?」という現実離れした展開に、(もしかして、加賀野、死にかけてて「こんな人生だったらよかったのに」と別の人生を夢で見ているのかい?)と、心配になったほどだ。
ネタバレを避けて紹介すると、地域との関わりを持っていなかった加賀野が、ご近所さんと仲良くなり親切にしてもらっているという描写がある。この時点で性善説が甚だしい。現実の世界で「本質的に引きこもりの素養をもつ人間」に親切な人というのは、十中八九、宗教かネットワークビジネスの関係者である。うっかり信じてはいけない。加賀野への見返りを求めない親切が存在しているのは、智が種まきしたから。そういう解釈なら、ギリギリ成り立ちそうだ。よりおとぎ話感の強い展開は、メインエピソードで楽しめる。
心が温かくなる話というのは、おとぎ話の中にしかないものなのだ。現実的な物語を書こうとすれば、まさに加賀野が書く面白くなさそうな小説になってしまう。だから、小説に現実はなくていい。
おとぎ話だと揶揄したものの、「仕事上の付き合い」に限定すると、私にとっての「智」たちは現実に存在した。彼女たちに感謝の念を送りたい(怖い?)。そして、プライベートでも「智」に出会えるかもしれないという希望は、心の片隅に温めておきたいと思った。
最後に、加賀野にとって都合がいいラストだったため、加賀野に自分を投影した私は楽しく読めたけど、シングルマザーが読むと腹が立つかもしれない。